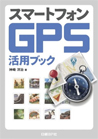サッカーのワールドカップが目前に迫ってきた。なんでか解らないけれどワクワク感が止まらない。先日は横浜国際でFマリノス-ガンバの試合を観た。海外移籍をひかえた中村俊輔選手にとってFマリノスでの最終ホームゲームということで少し話題になったゲームだった。結果は俊輔のVゴール。ジラされたが、有終の美を飾ったという印象かな。サポータも大喜びだった。それにしても日本代表のユニフォームは格好悪い。どうにかして欲しい。あの肩口の3本線なんかアディダスの企業イメージデザインじゃないのよ。代表たるユニフォームのデザインに一企業のイメージを入れるなってば。あのレブリカ・ユニフォーム来てTV観戦してたら、寝巻き着ているみたいでしょ。仕方がないから他の国のレプリカ・ユニフォーム来て応援するか。ベルギーとか(をいをい)。閑話休題。
■ハードディスクのおはなし
僕の元々のバックグラウンドはハードディスクのサードパーティだ。パソコンと言えばNECのPC-9800(通称キューハチ)を指していると言っても過言ではないほど、NECの独壇場だった。もちろん、シャープのX68000や富士通のFMタウンが、それぞれゲームの画像処理の高速性やCD-ROMマルチメディアの魅力を謳い、ユーザ獲得にやっきになっていたが、パソコン業界とはかくも不思議なりき、決して最高の性能が支持されるわけではないのである。
インターネットマンが執筆した
セキュリティの教科書 好評発売中 |
体系的に学ぶ
インターネットセキュリティ
神崎洋治、西井美鷹著
日経BPソフトプレス 1,890円
・ファイアーウォールのしくみ
・ウイルス、ワンクリック詐欺
・プライベート画像や
機密情報流出事件
など、セキュリティのしくみを体系的に解説、対策を初心者にも解るようにていねいに、かつ、詳しく解説。
>>詳細を見る
|
|
|
|
|
そんな頃、みんなが欲しがる周辺機器の筆頭と言えば「ハードディスク」だった。パソコンと言えばキューハチ、OSといえばMS-DOSだった頃、パソコンはフロッピィから起動していた。電源を入れると「ピボッ」という音がして、ガッコンガッコンガッコンと強烈な音を立てて、フロッピィからOSが読み込まれる。そんな儀式を経て、MS-DOSの真っ黒な画面が愛想なく起動するのである。
ゲームをするときはゲームのフロッピィを挿し、ワープロをするときはワープロのフロッピィを挿す。たかがちょっとの作業のためにフロッピィを何枚も差し替えて起動することもしばしば。その遅さと言ったらワンダホーのひと言に尽きる。
Windowsからパソコンを始めた人には想像もできない光景に違いない。
なにせ、100MBのハードディスクが10万円以上もする高価なシロモノだった頃の話である。
■みんなハードディスクが欲しかった
ハードディスクは羨望だった。キューハチ本体の背面にあるスロットのふたをドライバーではずし、接続のボードを挿し込む(キューハチは今のWindowsパソコンと違ってパソコン本体のカバーを開けずに拡張ボードを装着することができた。なんだドンドン退化しているのか)。そこからケーブルを接続し、外付けハードディスクを付ける。このハコの中にMS-DOSがすっぽり入り、なおかつソフトウェアまでがボンボン入ってしまう。それはどうやら「インストール」と呼ばれるらしい。しかも、なんと高速なことか。電源を入れたかと思うたら、もうわらわの目の前には色鮮やかなメニュー画面が燦然と輝きを放ち候・・。ハードディスクメーカーが用意したメニューソフトにはインストールしたアプリケーションがきちんと整理して表示され、フロッピィを入れ替えながら起動していたあの悪夢は(更にさかのぼると、パソコンにカセットテープを接続してピーガー言わせていた狂気の時代は)いったいなんだったろうかと顧みるのであった。とまぁ、それほどにハードディスクの存在は崇高だったのである。
「このハードディスクこそが僕の未来だ」「きっといつかは僕らもハードディスクになってやる」と直感し(意味不明)、ハードディスクメーカー(正確にはサードパーティ)の門を叩き、そこで製品開発、広報、展示会、広告宣伝、マニュアル制作などを担当させてもらうことになる。この分野の企業をサードパーティ呼ぶのは日本独特の文化である。通常、サードパーティとはメーカーの下請けや外注先を指すことが多いが、日本ではドライブを外付けユニットに組込み、パッケージ化して販売し、なおかつ当時はキューハチを研究し、独自の技術で高速で使いやすいボードなどを開発する技術力を持った(今で言う)ベンチャー系企業を「サードパーティ」と呼称していた。
ハードディスクに囲まれた毎日は幸せだった。自分のお金で買った初めてのハードディスクは100MB(メガバイト)の外付けハードディスクだった。当時の外付けハードディスクはSCSI(スカジー)という規格のものだった。
■いまではすっかり1台で160GB!!
いま、目の前にマックストアの外付けハードディスクが置いてある。風情はそれほど大きな違いはないが「160GB(ギカバイト)」と書いてある。ふーむ。160GBと言えば、初めて買ったハードディスクの約1600個分と同じだけの容量だ。ふーむ。1600個かぁ。ふーむ、せ・・せんろっぴゃっこぉぉぉぉ?
世の中はなんと奇天烈なことか。あの頃のゲームはいったい何千本インストールできるのだろう、なんて考えることはないが、それにしても進化ここに極まれり、というところだ。(極まってはいない・・きっとまだまだまだ続く) |

マックストアの外付けハードディスク『Personal
Strage 3000XT』。高速なIEEE1394インタフェースを装備し、160GBの大容量を誇る。ドライブはULTRA
ATA133対応だ。
|
■キューハチ時代の終焉
というわけで、サードパーティはキューハチの時代に外付けSCSIハードディスクでたいそう儲けた。もちろん自社開発のユニーク技術も多く、独特の世界観を作っていた。だから多くのユーザをこの手で幸せにしたという実感もあった。サードパーティにとってそれは絶頂期だったと言える。その頃、海外からIBM
AT互換機の足音がひたひたと聞こえ始めていた。ITの黒船である。それはパソコン業界やサードパーティ、ハードディスクの歴史にとっても「革新」であり、「維新」であり、「改革」のはじまりであったろう。まさに大きなうねりだった。
グローバルスタンダード・・いまならきっとそう呼んだ。キューハチの独壇場という特殊な市場に欧米の標準がやってきたのである。今で言うWindowsパソコンの祖先だ。ハードディスクは最初からパソコンに内蔵されているのが基本だった。外付けハードディスクのように、美しい筐体・・つまりはボディやそのデザインはない、接続するためのインタフェースボードもその高速技術を争うこともない・・・ハードディスクは剥き出しのまま、部品としてパソコンに収まっていた。それがIBM
AT互換機の世界だった。
僕は言った。
「僕たちはこれから何をすればいいのだろうか?」
NECは僕たちサードパーティに対して急に積極的にアプローチし始めた。今までほとんどキューハチの技術情報を公開することはなかったのに、開発するための情報をどんどんと公開してよこした。IBM
AT互換機の侵略にキューハチが脅威を感じている証拠だった。国内サードパーティを抱き込み、日本固有のキューハチ文化を守りたかったのだ。しかし、それはすなわち時代の終焉が近いことを示しているに過ぎなかったのである。
いま、目の前に数台の内蔵ハードディスクがある。IDEとか、ATAとか呼ばれている仕様のハードディスクだ。Windowsによってキューハチは絶滅し、Windowsパソコンと呼ばれる文化がやってきた。そこにはこのハードディスクが納められ、ユーザに無限の楽しさを与える源となっている。容量は160GB。大容量化はとどまるところを知らない。
|
|













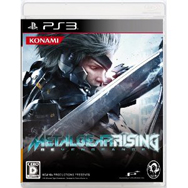




 第1巻は 99 円キャンペーン中
第1巻は 99 円キャンペーン中